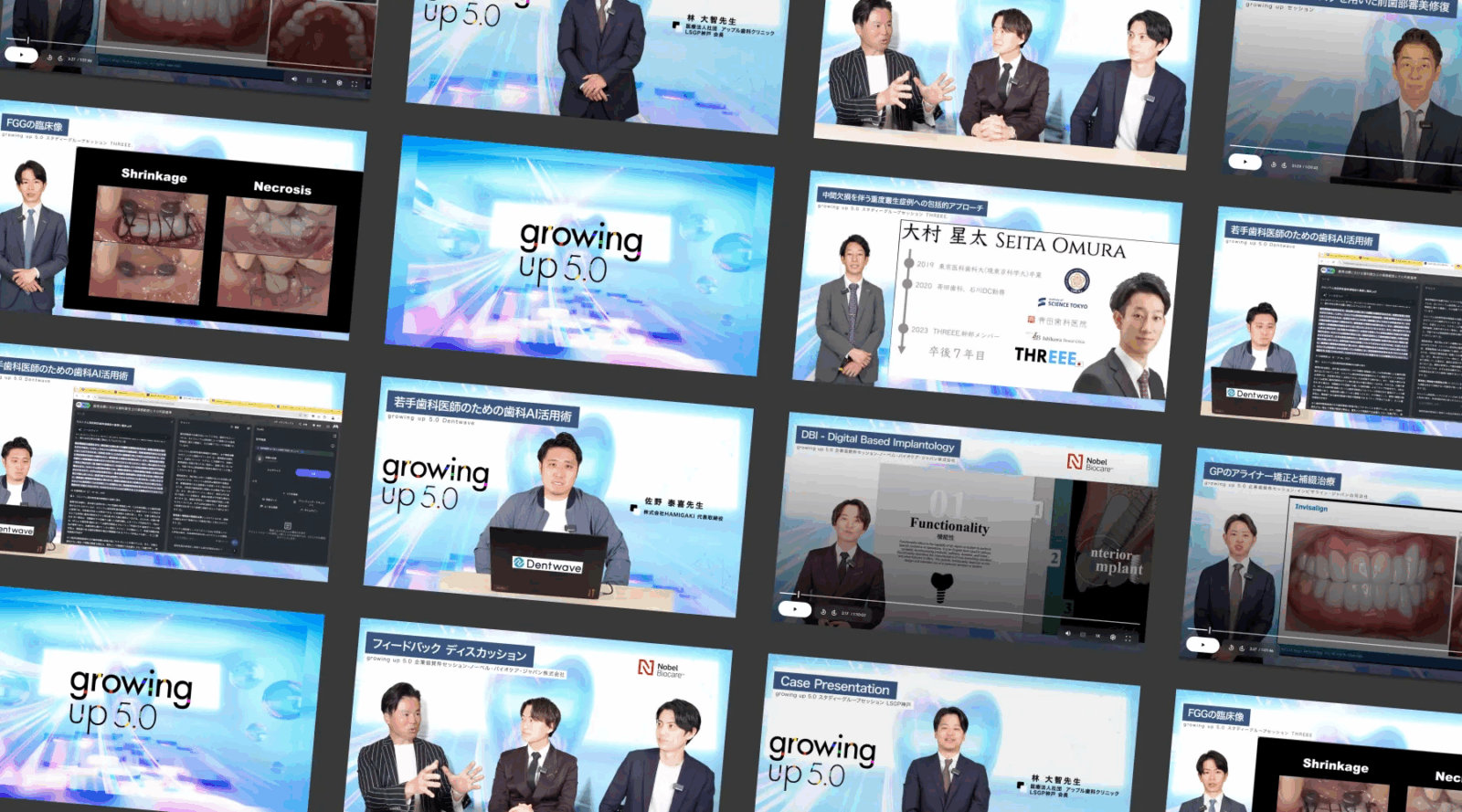病院・クリニック・歯科医院でのホームページ制作について、「ホームページは持っているけれど、集客(集患)に繋がるかわからない」「新規開院するが、ホームページは必要?」など、悩んでいる人もいるでしょう。
病院やクリニックなどの医療機関のホームページは、いわゆる名刺代わりのものが多く、かつてはそれが一般的でした。しかし、近年はホームページの役割が変わりつつあります。
そこで、今回は病院、クリニック、歯科医院のホームページが必要な理由に加え、現状の課題や、押さえるべき3つのポイントを紹介していきます。自院のホームページ制作について悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。
病院・クリニック・歯科医院にホームページは必要?
口コミや地域の看板などから、どの病院やクリニックに行くかを決めることが一般的でした。しかし、今ではインターネットでの情報収集が主流となり、病院・クリニック・歯科医院にとってホームページ制作は欠かせない存在となっています。
スマートフォンの普及により、誰もが気軽に検索できて、病院やクリニック、歯科医院などの医療機関の情報を比較・検討する時代になっています。
ここでは、なぜホームページが必要なのかについて、詳しく見ていきましょう。

スマートフォンでの検索
体の不調を感じたり、特定の治療を検討したりした際、まずスマートフォンで検索をおこう患者さんが多いでしょう。「地域名+診療科」や「症状+治療法」など、さまざまなキーワードで情報を探します。
検索したときに、クリニックの公式ホームページがない、あるいはスマートフォンに対応していない(レスポンシブデザインではない)医療機関は、検索結果で不利になってしまうのです。
また、スマホ検索時には「今日診察できるか?」「最寄り駅から近いか?」「予約できるか?」など、即時性・利便性を重視した情報を確認したいというニーズが強まります。患者さんのニーズにスムーズに応えられる構成・導線がないと、他院に流れてしまうことがあるのです。
患者が病院を選ぶ時代
昨今はインターネットの普及により、「どこで診てもらうか」を自分で調べて、選択する時代です。全国にはコンビニの数よりも多いとされる歯科医院をはじめ、多くのクリニックが存在し、患者さんはさまざまな情報を比較検討して受診する医療機関を決めます。
ポータルサイトや口コミサイトの情報も参考にされますが、口コミ情報だけでは伝えきれない、医療機関独自の強みや詳細な情報を求めているのが患者さんの実態ともいえるでしょう。
たとえば、インプラントや矯正といった専門的な自費診療を検討している患者さんは、治療内容、使用する機器、治療費、医師の経験・実績について、複数の医院を徹底的に比較します。
患者さんに選んでもらうためには、必要な情報をきちんと公式ホームページに載せておくことが大切なのです。反対に、情報が乏しい、または分かりにくいホームページでは、他院に患者さんを持っていかれてしまう可能性が高まるでしょう。
ホームページは安心感につながる
はじめて訪れる医療機関に対し、患者さんは少なからず不安を感じるものです。治療に対する不安、待ち時間への懸念、院内の雰囲気への緊張など、不安要素は多岐にわたります。
ホームページは、不安を事前に解消し、「安心感」へとつなげるための重要なツールとなるのです。
まず、院内の写真(待合室・診察室・検査機器など)を掲載することで、医院の雰囲気を可視化できます。
次に、診療の流れや初診時の手順、よくある質問(Q&A)、料金目安・保険適用範囲などの情報を丁寧に提示しておくことが大切です。「何を事前に準備すればいいか」「どれくらい時間がかかるか」「診察料の目安は?」といった疑問を先回りして解消しておくことが信頼につながります。
さらに、院長・スタッフ紹介、医師のメッセージや想い、日常の取り組みなどを載せることで「人の顔の見える医院」へと印象を変えられます。
また、ホームページがきちんと更新されているかどうかも安心感の指標になります。更新が数年止まっているサイトは、「運営が止まっている」「対応が遅そう」という印象を持たれやすくなってしまいます。
病院・クリニック・歯科医院のホームページの現状と課題
病院・クリニック・歯科医院など多くの医療機関がホームページを保有していますが、すべてが効果的に機能しているわけではないでしょう。現状、多くの医療機関のホームページ制作には、以下のような課題が見られます。
- 古いデザインやスマホ非対応
- 更新が止まっている
- 病院・クリニック・歯科医院の雰囲気が伝わらない
古いデザインやスマホ非対応が多い
10年以上前のテンプレートやCMS(コンテンツ管理システム)で構築されたまま、自院のホームページを放置している病院・クリニックもあるのではないでしょうか。
医療分野では、清潔感や先進性といった印象が信頼に直結しやすいです。見た目が古いことは「古くさい」「活気がない」というネガティブな印象がマイナス評価につながる可能性があります。
また、スマートフォン対応されていない(レスポンシブデザインではない)ケースも問題です。ほとんどの患者さんがスマートフォンで検索することから、PC表示のままの小さな文字や操作しにくいページでは、ユーザーはすぐに離脱してしまいます。
更新が止まっている
制作したあとの運用が疎かになってしまうケースも多数あります。
情報が更新されていないホームページは、「診療が適切におこなわれているのだろうか?」「本当に情報は正しいのだろうか?」といった患者さんの不安につながり、「信頼できない医院」という印象を与えてしまうでしょう。
休診日や診療時間の変更など、最新情報を常に更新しておきましょう。
病院・クリニック・歯科医院の雰囲気が伝わらない
写真が極端に少ないサイトや文章だけで構成された医院ホームページも課題のひとつです。「どのような施設なのか」「スタッフはどんな人なのか」「どのような診療方針か」が伝わらず、患者の安心感が得られにくくなります。
とくに、歯科医院に対して「怖い」というイメージを持つお子さんや親御さんにとっては、院内の明るい雰囲気やスタッフの優しい笑顔を写真で伝えることが、来院への大きな安心材料となる場合もあります。
病院・クリニック・歯科医院で成果が出るホームページの3つのポイント
病院・クリニック・歯科医院のホームページ制作で成果を出すには、患者が求める情報にスムーズにたどり着け、信頼感を抱ける構成が必要です。ここでは、成功につながるポイントを紹介します。
患者目線での導線設計
ホームページは、患者さんが迷うことなく、求めている情報にたどり着けるように設計されていることが大切です。これをユーザビリティといいます。
①知りたい情報への最短ルートを確保
- 診療時間、休診日、アクセス情報、電話番号はトップページの目立つ位置に配置する。
- 予約システムや問い合わせフォームへのボタン(CTA:Call To Action)は、全ページからすぐにアクセスできる位置に、目立つ色で設置する。
②分かりやすいメニュー構成
- 自分がどの症状で、どの科を受診すべきか分からない患者さん向けに、「症状別」「お悩み別」のコンテンツも用意する。
- スマートフォンのために、ハンバーガーメニューなどを用いて、必要な情報がすぐに見つけられる設計にする。
③専門用語をわかりやすくする
- 患者さんが理解できるよう、専門的な医療用語はわかりやすい言葉に置き換えたり、注釈をくわえたりするなど、患者さんに寄り添う表現を心がける。
わかりやすい設計をおこなうことで、患者さんはストレスなく必要な情報にたどり着きやすくなります。50代以上の方など、ウェブ利用に慣れていない層への配慮も重要です。
スマホ対応とわかりやすいデザイン
いまや患者さんの多くは、病院やクリニックを探す際にスマートフォンを利用しています。そのため、パソコンでしか最適に表示されないホームページでは、閲覧の途中で離脱されてしまう可能性が高くなります。スマホで快適に閲覧できるレスポンシブ対応は必須です。
また、ただ対応していればいいのではなく、「文字が小さすぎないか」「ボタンが押しやすいか」「情報が整理されていて直感的に操作できるか」 といった使いやすさも重要です。情報が見つけにくい、読みづらいといったストレスは患者さんの不安や不信感につながります。
とくに、医療機関のホームページでは、「診療科目」「診療時間」「アクセス」といった基本情報をすぐに確認できることが大切です。わかりやすいデザイン設計は、患者さんの安心感と信頼感を高め、来院のきっかけを作るでしょう。
院長・スタッフの「人柄」が伝わるコンテンツ
患者さんは、治療を受ける際、医師やスタッフとの相性も重視しています。長期的な治療や専門性の高い治療の場合、医師の「人柄」や「治療に対する想い」が、選ばれる決め手となります。
具体的には、次のような要素を取り入れると効果的です。
- 医師・スタッフ紹介ページ:顔写真、略歴、専門性、職務に対する思いや日常の趣味・人柄
- コラム・ブログ・お知らせ:専門知識や健康情報の発信、医院の日常
- 患者の声(体験談):ただし、医療広告ガイドラインに抵触する表現を避ける必要あり
- 360度写真・動画ツアー:院内・診察室・設備を見られるようにする
- Q&A形式の対話的コンテンツ:患者が抱えやすい不安に先回りして答える
ただし、医療広告ガイドラインにおいて、「体験談」「他院との比較」「誇大表現」といった表現には制限があります。たとえば、優良比較や過度な主張、治療効果を断言するような文言は禁じられています。
体験談を掲載する際は、実例だけでなく、典型的な注意書き(個人差あり・効果を保証するものではない旨)を併記するなど、表現に配慮しましょう。
参考:「厚生労働省:医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」
病院・クリニック・歯科医院のホームページはスタッフ採用にも効果的
病院・クリニック・歯科医院のホームページは、集客(集患)に向けた情報発信だけでなく、看護師や歯科衛生士などの採用活動にも効果を発揮します。
求人サイトだけでは伝えきれない医院の雰囲気や理念、働く人たちの想いを発信できるのが、ホームページの強みです。
ここでは、求人活動でホームページを利用するメリットとポイントを紹介します。
応募者はホームページを必ずチェックしている
看護師や歯科衛生士など、医療関係の求職者が就職先を探す際、必ずといってよいほどホームページを確認します。職場の雰囲気や医院の理念などは、求人票だけでは伝わりにくいためです。
数多くある医療機関のなかから、自院に応募してもらうために、職場の雰囲気や理念、働く人の声を発信しておきましょう。
詳細情報を発信して応募者とのミスマッチを防ぐ
採用後の「思っていた職場と違った」というミスマッチは、早期離職につながる原因のひとつです。求人サイトでは掲載できる情報に限りがありますが、自院のホームページなら自由に情報を記載できます。
応募者とのミスマッチを未然に防ぐために、ホームページに「採用情報ページ」を作り、給与、福利厚生、具体的な業務内容や職場の雰囲気など、求人に関する具体的な情報を積極的に発信しましょう。
働く人の雰囲気や環境を伝えることが信頼につながる
求職者は、給与や勤務時間といった条件面だけでなく、「スタッフ同士の関係性」「院長の考え方」「働きやすい環境かどうか」も重視します。
写真や動画を使って日常の様子を紹介したり、スタッフインタビューを掲載したりすることで、働くイメージを具体的に伝えられるでしょう。
病院・クリニック・歯科医院のホームページ制作についてよくある質問
医療機関がホームページ制作を検討する際、よく寄せられる疑問点を Q&A 形式で整理しました。
制作期間はどれくらい?
制作期間は、サイトの規模や機能、原稿・素材の準備状況によって大きく変動します。一般的に、小規模なクリニックサイトで、原稿作成もスムーズに進む場合、1.5〜3か月程度を目安です。
ただし、以下のようなケースでは、さらに期間が必要になります。
- 大規模な病院サイト(多部署、多診療科)
- 写真撮影や動画制作からおこなう場合は撮影スケジュールによって期間が変動します。
- 予約システムや電子カルテとの連携など、複雑なシステム開発を伴う場合。
- 医療広告ガイドラインのチェックに時間を要する場合。
また、準備段階で情報整理(設計・構成・テキスト起こし・素材選定など)に時間がかかることがあるため、スケジュール調整に余裕を持っておくことが重要です。
費用感は?
ホームページ制作の費用は、デザインの自由度・機能追加(予約システム、問診フォーム、CMS構築、動画)・写真撮影の有無などによって幅があります。 医療機関向けでは、30万円〜150万円程度がひとつの目安として挙げられます。ただし、さまざまな機能を付ければ200万円を超えるケースもあります。
また、制作費だけでなく、ドメイン・サーバー費用(月額・年額)、保守・更新代行料、SSL証明書費用なども念頭に置きましょう。制作会社の中には、初期構築費を抑えて、月額制で運用サポートを提供するプランを用意しているところもあります。
既存サイトのリニューアルは可能?
実際、多くの医療機関が「古いデザイン」「スマホ非対応」「情報不備」などを理由にリニューアルを選んでいます。
リニューアルは、古いデザインやスマートフォン非対応といった課題を解決し、最新の集客(集患)ノウハウを取り入れる絶好の機会です。リニューアルでは既存ドメイン・URL構造・コンテンツをできる限り引き継ぎつつ、新しいデザイン・スマホ対応・SEO構成を追加できます。
ただし、現行サイトの構造が極端に複雑であったり、CMSやデータベースが古い仕様であったりすると、移行作業や調整に手間がかかる可能性があります。
医療広告ガイドラインに対応してる?
医療機関のホームページは、厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」に準拠する必要があります。
たとえば、次のような表現には注意が必要です。集客
- 「他院より優れている」「日本一」「No.1」など、比較優良広告とみなされる表現は原則禁止です。
- 「完全に治る」「必ず安全」など、過度な断言表現は誇大広告となる可能性があります。
- 治療前後の写真(ビフォー・アフター)を掲載する場合、十分な説明や注意書きを付けずに掲載すると規制対象となります。
制作会社を選ぶ際には、医療広告ガイドラインに精通しているか、表現チェック体制があるかを確認することが大切です。
参考:「厚生労働省:医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」
まとめ
病院・クリニック・歯科医院におけるホームページ制作は、集客(集患)のための大切な戦略ツールとなっています。患者さんがスマートフォンで情報を検索し、「安心」と「信頼」できる医療機関を選ぶ現代において、公式ホームページは欠かせません。
多くの医療機関ホームページに見られる「古いデザイン・更新停止・雰囲気が伝わらない」という課題を克服するには、導線設計、スマホ対応・わかりやすいデザイン、院長・スタッフの人柄を伝えるコンテンツ設計の3点を押さえることが大切です。
そして、制作を依頼する際には、期間・費用・リニューアル可否・医療広告ガイドライン対応といった点をしっかり確認しましょう。
益田工房では、医療機関のホームページ制作の実績が多数あります。もし「今のサイトを見直したい」「新しく作りたい」とお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
病院、クリニック、歯科医院のホームページ制作実績
益田工房では、これまで数多くの医療機関・歯科医院、歯科医療業界のセミナー、イベントの仕事をさせていただいております。豊富な経験と実績から、課題解決に向けたデザインを提案させていただきます。
以下に、代表的な制作実績を紹介させていただきます。
済生会江津総合病院

金沢大学附属病院 総合診療共創センター(ティザーサイト)
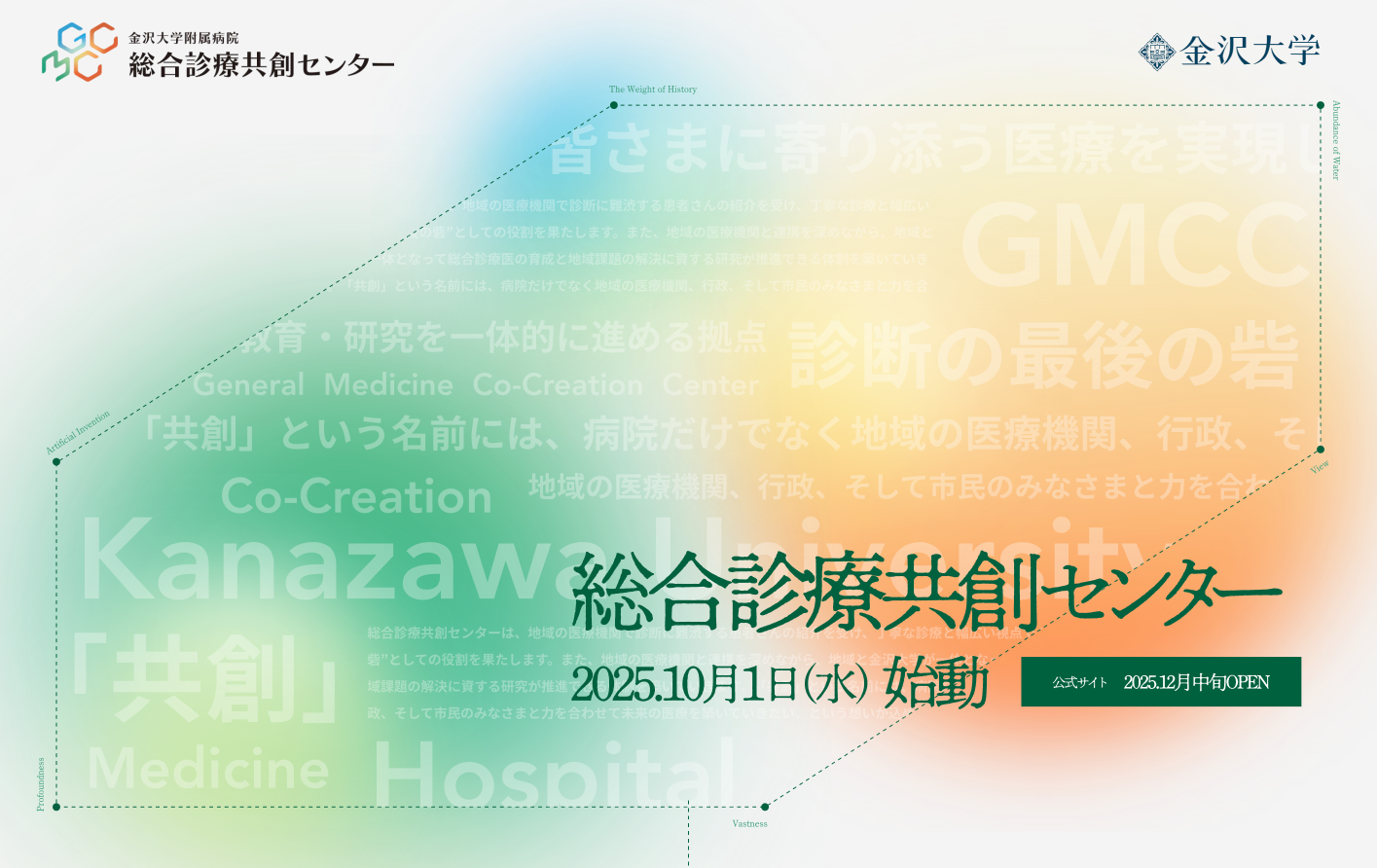
島根大学医学部 しまね総合診療センター(GOOD DESIGN賞 2022金賞受賞)
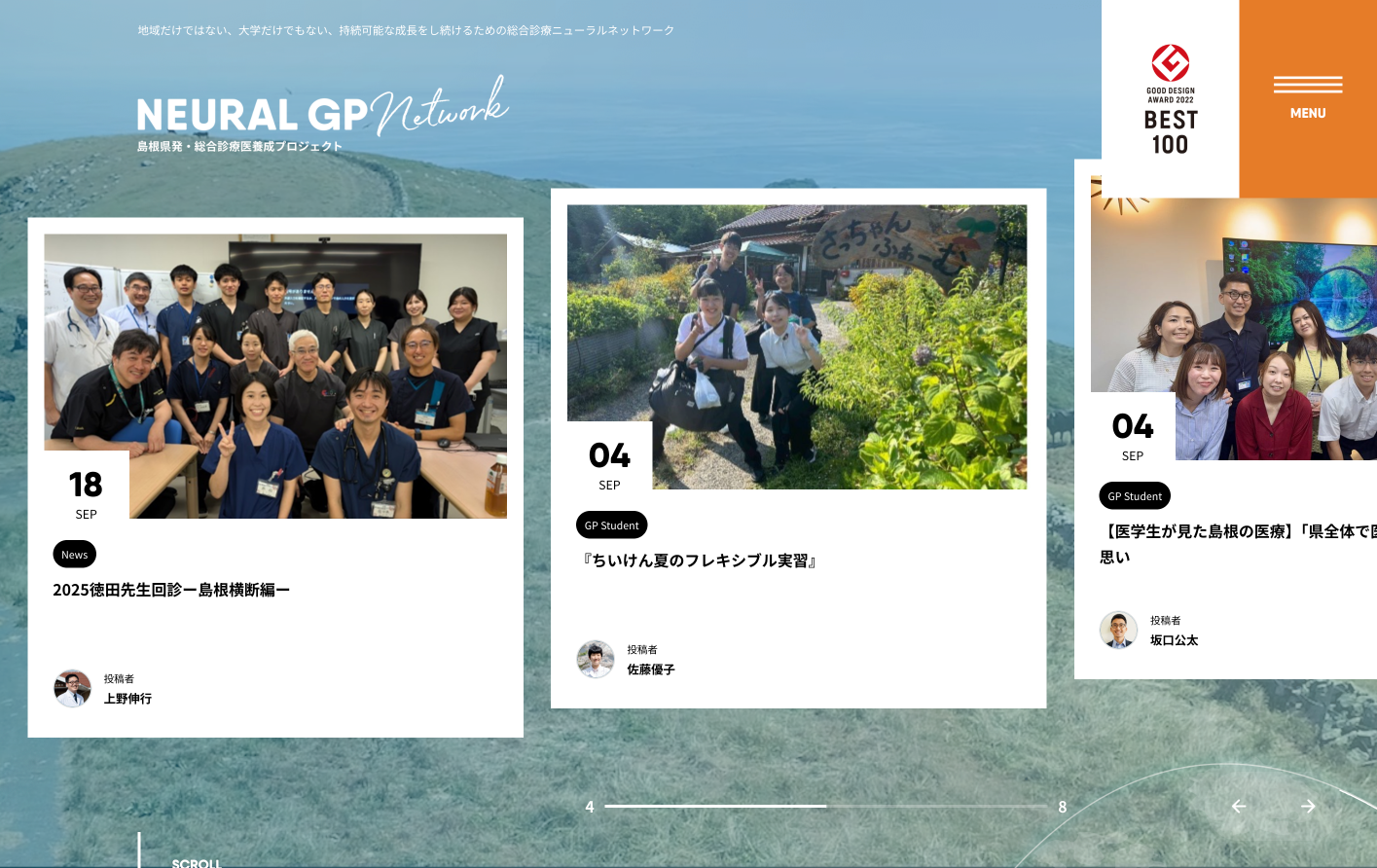
第15回 日本ポイントオブケア超音波学術集会 特設サイト

誠創会 あさがおクリニック 採用ショート動画制作
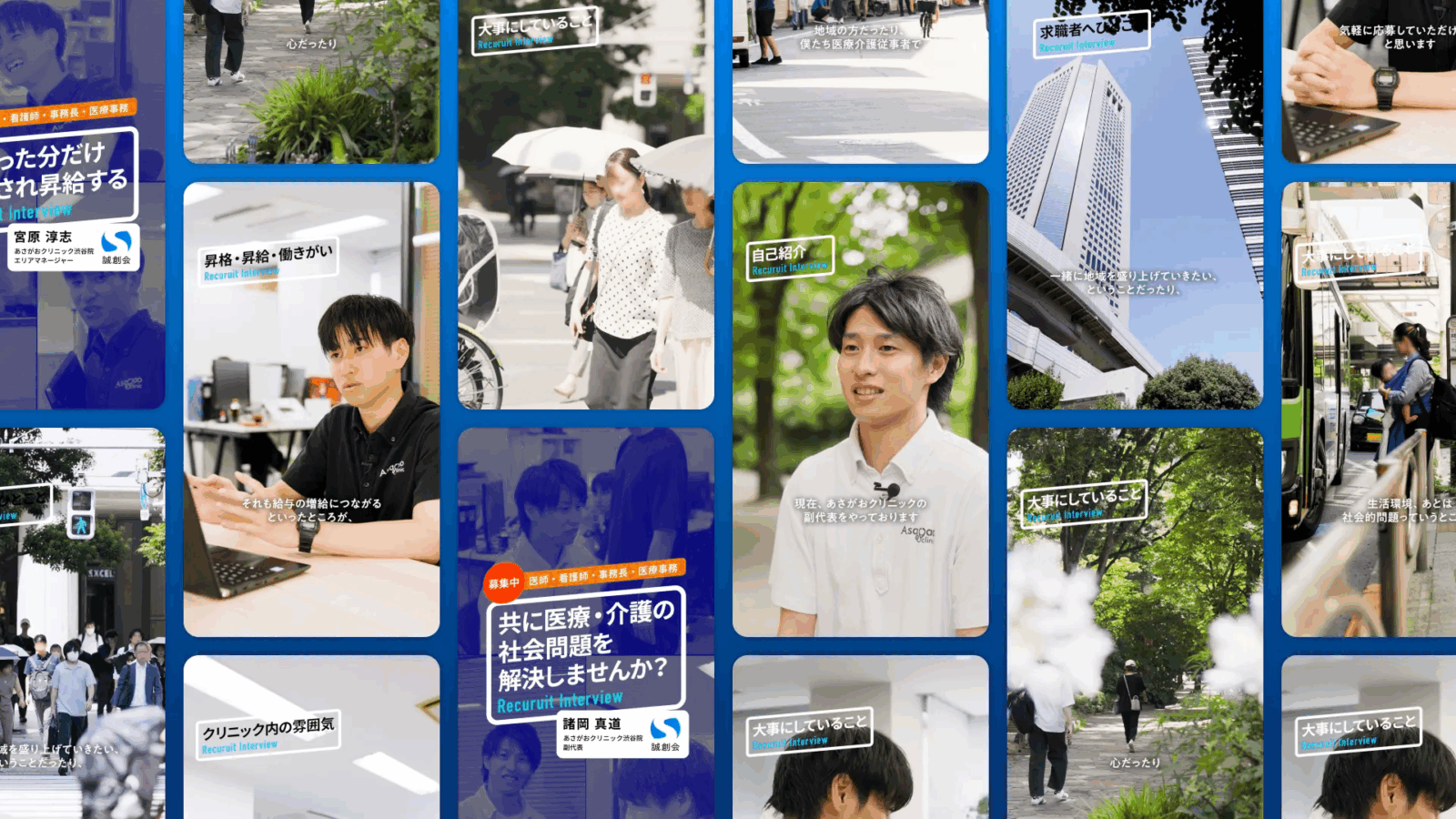
歯科医向け オンラインセミナー Growingup 5.0